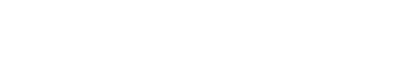2025/04/01 コラム
紅茶のはなし
紅茶は、緑茶や烏龍茶のような中国茶とは異なる種類の木の葉から作られるように思われているかもしれませんが、ツバキ科の常緑樹などの同じ木から芯芽や若葉を加工して作られています。
これらの茶葉を製造するには、加工方法が異なります。
緑茶は、摘み採ってからすぐに加熱して、葉のなかに含まれる酸化酵素の働きを止めて製茶工程を行います(不発酵茶)。
烏龍茶のような中国茶は、葉のなかに含まれる酸化酵素をある程度働かせてから、釜などで炒りながら熱を加えますが途中で止めてしまいます(半発酵茶)。
紅茶は、摘んだ葉をしおらせてよく揉み、褐色に変化するまで酸化酵素の働きを強めてから乾燥させます(完全発酵茶)。

紅茶は、17世紀頃にオランダ人が中国からヨーロッパに伝えたと言われています。
紅茶は、葉の産地や収穫期、茶葉の形状などで区分されています。
例えば、産地ではインドにはダージリン、アッサム、ニルギリなどがあり、ダージリンはマスカットのような香りがあると言われています。
またスリランカにはウバ、ディンブラなど、中国にはキーマンなど、他には東アフリカ、南米などに産地があります。収穫時期では、「クオリティ・ピーク・シーズン」といわれる品質が最高になる収穫時期があります。
ダージリン茶では、4月頃にファースト・フラッシュ(一番摘み)が収穫出来ます。
6~7月には、セカンド・フラッシュ(二番摘み)、10月頃には、オータムナル・フラッシュ(秋摘み)のように3回のシーズンがあり、収穫時期を区分して取引されています。
セカンド・フラッシュ(二番摘み)はダージリン特有のマスカットフレーバーが際立つと言われています。
また、茶葉の形状では、リーフティー(葉茶)の形やブロークンティー(砕茶)に分類されています。
リーフティは紅茶をいれる時に1枚ずつ茶葉が元の姿に戻ります。
紅茶をおいしくいれるためには、ティーポットを温めておく、沸騰したての空気を含ませた湯を使う、茶葉を蒸らす間はゆっくり待つのが望ましいとされています。
茶葉の種類によってはポットの中で葉が上下運動することをジャンピングと言います。
沸騰直後の湯はジャンピングが起こりやすいとされています。茶葉1枚1枚から味や香りが抽出されます。
また、飲み方にあった茶葉を選ぶことも大切です。
ストレートティーにはダージリンを、ミルクティーにはアッサムやウバが合うとされています。
紅茶には身体にうれしい成分が含まれています。
紅茶のうま味や甘味、香りをもたらすテアニンは気分をリラックスさせる効果もあるといわれています。
タンニンには抗酸化作用が、カフェインには集中力を保つ作用や、疲労回復効果が期待されます。
たくさんの種類のなかから選んだ紅茶を、くつろぎの時間に取り入れてみることは、楽しみが増えることに繋がるかもしれません。

参考資料
杉田浩一ら編(2017). 新版日本食品大事典. 医歯薬出版. 266-270頁
日本紅茶協会編(2022). 紅茶の大事典. 成美堂出版. 10-81頁